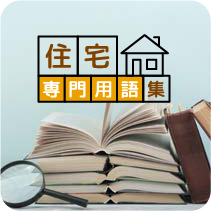-
ジタクの備え NEW 2025.09.05
身近にできる「フェーズフリー」の取り組み

「日常」「非日常」区別しない
普段の生活に防災取り込む
いつもの暮らしを送る日常と、災害が起きた非日常の垣根をなくす「フェーズフリー」の考え方が広まっている。普段の生活の中で、どんな時でも役立つ物やサービス、施設などを利用することが、有事に備えることにつながる。身近にできるフェーズフリーの取り組みについて、山梨県防災危機管理課の中嶋正樹課長に聞いた。

長期保存が利くレトルト食品や缶詰などを多めに買い、古い物から使ってその都度買い足す「ローリングストック」は、普段の生活を送りながら自然に食料品が備蓄され、災害時でも確保できている状態となる。物資の支援が届くまでの間、最低でも1人あたり3日分、できれば1週間分は備蓄したい。災害用と思ってそのまま食べるのではなく、煮たり炒めたり、食材を加えたりしてアレンジすることで、いつもの食卓でも十分楽しめる。
食料と合わせて準備したいのが携帯用トイレ。トイレを我慢するために、食事や水分を控えると健康に影響が出る恐れがあり、常備しておくと良いだろう。ポリ袋と凝固剤がセットになった携帯用トイレは、断水になっても便座を使って、用を足すことができる。車の中に置いておけば、旅行やドライブで渋滞に巻き込まれた際にも使える。トイレットペーパーやティッシュペーパーは常に1カ月分以上を持っておくと、被災時のパニック買いを避けることができる。
車のガソリンは半分まで減ったら満タンに。以前、被災地のガソリンスタンドで燃料を求める車が行列を作り、渋滞が問題になった。常にある程度の燃料が入っていれば、移動はもちろんのこと、冷暖房を使ったりスマートフォンを充電したりできる。
キャンプ用品は、元々電気やガスがない屋外で楽しむレジャーの物なので、災害時にも使いやすい。電池式のランタンを寝室に置けば、おしゃれなインテリアにもなる。
山梨県が2023年に発表した地震被害想定調査では、被災した際、自宅や車中など避難所以外での避難を選択する県民も少なくないと予想されている。住宅の耐震化率が向上していることもあり、在宅避難生活を送れるような環境を日ごろから整えておくことは重要だ。
フェーズフリーの考え方は、普段の暮らしの延長でできる防災。日常の中に少し工夫を取り入れるだけで、いざという時の備えになることを意識してほしい。
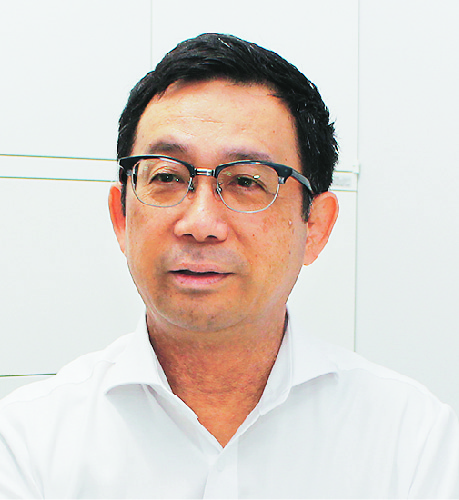
「災害時にも使えるものを普段から取り入れてほしい」と話す中嶋正樹課長